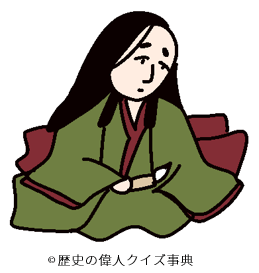「真田昌幸」は何をした人?したことを簡単に解説



真田昌幸は、1547年、現在の長野県上田市に近い真田郷で、真田幸隆の三男として生まれます。
真田幸隆は武田信虎に仕え、武田家の威光の下で成長する家系の一員として、真田昌幸は幼い頃から武士としての厳しい訓練を受けました。
真田昌幸は、7歳のときに武田家の人質として送られます。
武田信玄からの厚い信頼を得た真田昌幸は、若くして重要な任務を任されるようになり、特に第4次川中島の戦いでは、その軍略で名を馳せました。
武田家の崩壊後、真田昌幸は時代の変遷と共に主君を変えながらも、常に真田家の利益と存続を最優先に考え行動しました。
その過程で織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者と巧みに関係を築き上げたりもしました。
特に徳川家康とは、利害の一致と対立を繰り返す複雑な関係で結ばれていましたが、真田昌幸は真田家の安泰を守るために、その知略と外交術を駆使しました。
真田昌幸の大きな出来事の一つが、徳川家康に対する第1次上田合戦の勝利です。
この戦いでは、圧倒的不利な状況の中、昌幸は真田家伝統の知恵と戦術で徳川軍を撃退し、真田家の武名を天下に轟かせました。
しかし、関ヶ原の戦いでは、真田家は分裂し、真田昌幸は西軍に属して敗北しました。
その後、真田昌幸は息子の真田幸村とともに高野山に蟄居(自宅謹慎の刑罰)することになり、その地で静かな余生を過ごしました。1611年、昌幸はこの世を去りました
「真田昌幸」の年表(生涯)

| 年代 | 出来事 | 詳細な説明 |
|---|---|---|
| 1547年 | 出生 | 信濃の真田幸隆の三男として生まれる。武田信玄の家臣であり、後に大井氏支流の武藤氏の養子となり、武藤喜兵衛を名乗る。 |
| 1553年 | 武田氏の人質となる | 7歳で主家武田氏の人質となり、武田信玄の奥近習六人衆となる。 |
| 1566年 | 真田信幸誕生 | 嫡男の真田信幸(信之)が生まれる。 |
| 1567年(諸説あり) | 真田信繁誕生 | 次男の真田信繁(幸村)が生まれる。 |
| 1575年 | 長篠の戦い | 織田、徳川連合軍に敗退し、長兄の真田信綱、次兄の真田昌輝が討死。真田家の家督を継ぐ。 |
| 1582年 | 武田家滅亡 | 甲州征伐により武田家が滅亡。織田信長に恭順し、旧領を安堵される。 |
| 1585年 | 第一次上田合戦 | 徳川家康の軍を撃退し、次男の真田信繁を人質として豊臣秀吉に臣従する。 |
| 1600年 | 第二次上田合戦 | 徳川秀忠率いる徳川軍を食い止め、関ケ原の戦いを遅参させる。 |
| 1611年 | 死去 | 配流先の九度山で死去。享年65。 |

「真田昌幸」はどんな人物?わかりやすい解説とクイズ問題


真田昌幸は1547年に信濃国で生まれ、戦国時代から安土桃山時代にかけて生きた武将です。
幼名を源五郎、通称を喜兵衛とし、安房守とも称されました。
真田幸隆の三男として生まれ、後に真田家の基礎を築くことになります。
初めて戦場に立ったのは14歳の時で、川中島の戦いにおいて武田信玄のもとで初陣を飾りました。
武田信玄と、その後を継いだ武田勝頼に仕え、足軽大将(足軽大将:足軽で編成される部隊を率いる指揮官のこと)として活躍しました。
武藤喜兵衛として武藤家に入るも、兄二人が長篠の戦いで亡くなり、真田の姓に戻り、家督を継ぎました。
武田家滅亡後の不安定な情勢の中で、真田昌幸は独自の勢力を保持し拡大するために、巧みに周囲の大名たちとの関係を操りました。
特に上田城の築城とそれを中心とした城下町の開発は、小県郡の統一と真田家の基盤固めに大きく貢献しました。
真田昌幸の優れた戦術の例として、第一次上田合戦と第二次上田合戦が挙げられます。
これらの戦いでは、徳川家康の大軍を巧みな戦術で二度にわたり撃退し、真田家の防衛能力の高さを見せつけました。
しかし関ヶ原の戦いでの敗北後、真田昌幸とその家族は苦境に立たされます。
真田昌幸は昌幸の長男である真田信之の嘆願により、次男の真田幸村とともに一命を助けられ、紀伊国高野山麓の九度山に幽居(幽居:世を避けてひきこもって静かに暮らすこと)しました。
この地で真田昌幸は生涯を終え、その墓は和歌山県の善名称院にあります。
真田昌幸は生涯にわたり、一族のリーダーとしての役割や武田家から独立した大名としての地位の確立、そして巧みな戦術と戦略で名を馳せた武将です。
真田昌幸はどんな人物クイズ問題

【4択クイズ問題】
Q
真田昌幸が初めに仕えた家は誰の家でしょうか?

- A. 豊臣家
- B. 徳川家
- C. 武田家
- D. 伊達家
.png)
【穴埋めクイズ問題】
真田昌幸は1547年に信濃国で生まれ、戦国時代から安土桃山時代を生きた武将です。源五郎という幼名を持ち、喜兵衛と通称された昌幸は、( ① )の三男として真田家の基盤を確立しました。14歳で川中島の戦いに参加し、その後も( ② )、武田勝頼に仕え重要な役割を果たしました。兄二人が長篠の戦いで亡くなった後は、真田の姓に戻り家督を継ぎ、武田家滅亡後は独自の勢力を拡大しながら周囲の大名と巧みに関係を築きました。また、上田城の築城と城下町の開発により、小県郡の統一に貢献しました。第一次、第二次上田合戦では徳川家康の大軍を撃退し、真田家の強固な防衛力をあらわしました。( ③ )の戦いでの敗北後は苦境に立たされますが、昌幸の息子である真田信之の嘆願により、真田幸村と共に九度山に幽居し、そこで生涯を閉じました。昌幸は武田家から独立した大名として、そして巧みな戦術と戦略で名を馳せた武将です。
( )のことばを答えてみよう!
.png)
- 「真田昌幸」は何をした人?
- 「真田昌幸」の年表(生涯)
- 「真田昌幸」はどんな人物?→今ココ
- 「真田昌幸」が天才といわれる理由
- 「真田昌幸」の城
- 「真田昌幸」と真田幸村の関係
- 「真田昌幸」の逸話
- 「真田昌幸」の戦い
- 「真田昌幸」と徳川家康の関係



-150x150.png)
.png)
.png)